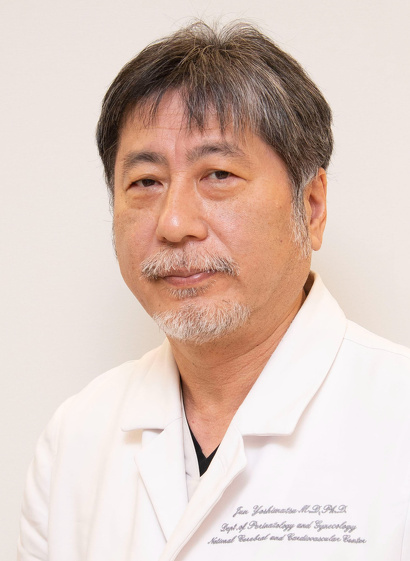ご挨拶
産科側理事を代表してご挨拶いたします。
腎と妊娠研究会は1991年に当時筑波大学腎臓内科成田光陽教授と同大産婦人科岩崎寛和教授が腎疾患合併妊娠に関する研究会として設立されました。以来、診療科横断的な学術団体として、それぞれの専門知識を交換し合うことのできる場を提供してきました。診療科の垣根を取り払い、腎疾患の専門家と産科の専門家がそれぞれの専門性をぶつけ合い、お互いの知るところ、知らざるところを確認し、腎疾患合併妊娠診療の新たな地平を開く、そのような志から始まった本会は我が国における診療科横断的な学術団体の嚆矢の一つと言えます。これまで、この分野における多くのトップリーダー達が本会の発展に尽力されてきました。設立時からの熱意は今も衰えることなく連綿と受け継がれ、腎疾患を有する女性の安全な妊娠、出産に寄与する様々な知見を生み続けています。個人的には2002年に私の恩師である宮川勇生大分大学教授(当時)の下、幹事として別府市での開催に関わってから14年後、2016年に大阪で会長として本会を開催したことをよく思い出します。この分野に関する熱意を持った研究、診療が脈々と受け継がれていることを実感する良い機会でもありました。
近年、注目されている概念としてプレコンセプションケアがあります。腎疾患は若年女性が有することが多く、妊娠というライフイベントにこの疾患を持って直面することが少なくありません。そのような女性に適切な医学的助言、管理を提供する際、本会の様々なアカデミックな活動により発信された知見が役立っています。また、このことは単に腎疾患のことにとどまりません。このような慢性の疾患を有する女性のプレコンセプションケアで、何が求められ、何が提供できるのか、腎疾患でのプラクティスはその他の疾患での良いモデルとなっています。プレコンセプションケアという概念はまさに今のものですが、そこには30余年にわたる本会の長きにわたる活動の歴史が寄与すること多いのです。
腎疾患を有する女性の妊娠、出産、そして、その前後の健康のために本会の果たす役割は重要で、内科医、産科医がその目的のために切磋琢磨し、手を携えてさらに多くの学術的財産を産み続けられるよう、会員一同の弛まぬ努力をお約束いたします
吉松 淳
代表理事、第26回大会長(国立循環器病研究センター 循環器病周産期センター長兼産婦人科部長)
研究会理事会の合議により研究会の代表職を設けることとなり、内科側の代表として初代代表理事に就任いたしました。腎と妊娠研究会は、1992年に第1回の学術大会を開催して以来30年以上の歴史を重ねてきた研究会です。妊娠・出産と腎臓内科とは密接な関わりがあり、現場では協働の機会が少なからずある一方で、お互いの経験を共有し、産科学・腎臓内科学それぞれの文化を尊重し合いながら共通のテーマで討議を重ねる場がなかったことを憂えた諸先輩方が本会をお作りになり、今日まで守り育てられて参りました。内科系と外科系をフュージョンし、産婦人科学会と腎臓学会の架け橋となる設立趣旨と立ち位置は当時他に類がない、極めてユニークな学術団体として両領域で認知され、研究会でありながら準公的な扱いを受けて参りました。この設立当初の存在意義は今日も色褪せることなく、毎年の学術大会では、相互理解への熱意、他領域への知的好奇心と敬意に溢れた雰囲気に大会長それぞれの個性が加わった独特の空気感の中で開催されています。医学的常識や共通認識が大きく異なる両領域からの症例報告、臨床研究及び基礎研究の演題はお互いにとって刺激的であり、依って立つ常識の違いが、時としてより本質的な議論への呼び水となる場面にもしばしば遭遇します。本研究会で討議されるテーマは多岐にわたり、妊娠高血圧症候群はその中心ではありますが、腎炎合併妊娠や膠原病、血管炎患者、透析患者、腎移植患者の妊娠管理など幅広い領域を扱う学術集会となっています。最近の当研究会の傾向として以下の2点を挙げたいと思います。一点目は他の学術団体とのコラボレーションが頻回に行われるようになったことです。母性内科学会とは当会の学術集会での共催企画、また母性内科学会が共催した他の学術集会におけるシンポジウムへの当研究会の参加など、相互の交流が慣例化しつつあります。二点目としては参加者のウィングの拡大が挙げられます。かつての当会は産科医と腎臓内科医の集まりでしたが、最近では看護師や助産師など多職種の参加が少しずつ増えています。産科医と内科医を中心に、両領域にまたがる産科医療に関係する全ての職種が一同に会する機会を提供する本研究会を、さらに有意義なものとしていくべく努力して参ります。
長谷川元
代表理事(埼玉医科大学かわごえクリニック 院長、埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科 特任教授)